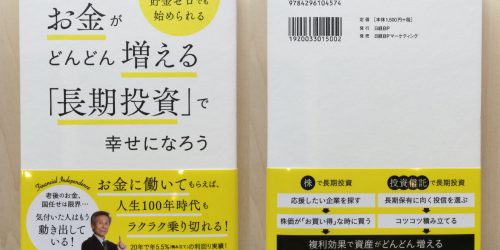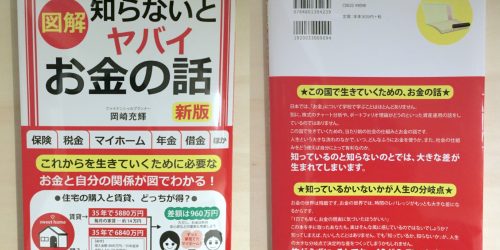人生のダイヤモンドは足元に埋まっている 強欲資本主義時代の処方箋

自分の本当の幸せとは
経済成長が鈍化している現代では、格差の拡大や資本の集中が大きな問題となっています。また金融の世界でも、リーマンショックの時、金融システムの脆弱性が発端となり、多くの人々の生活に大きな影響を与えました。本来、お金は人々の生活を豊かにするものであり、取引をより活発化させるものであったにもかかわらず、現代においては人々がお金のために蔑ろにされているのではないか、という疑念が出ています。
そこで本書では、投資信託会社バンガード・グループの創業者であるジョン・C・ボーグルが、強欲な世界に警鐘を鳴らし、本来的な人間のあり方について説いています。タイトルの『人生のダイヤモンドは足元に埋まっている』は、教訓を含んだ物語から付けられています。その物語は著者が共感しており、本の中でも紹介しています。大まかな内容は次のようなものです。
「古代ペルシャの裕福な農民が、さらなる富を求めて伝説のダイヤモンド鉱山を探したものの見つかることがなく、ついに海に身を投げた。そのころ、新しい土地の持ち主が現れ、敷地を見て回ると、大きなダイヤモンドを発見した。」
つまり、本当に大切なもの、価値のあるものは裏庭のような身近なところに転がっているということです。著者は、表面的な豊かさ、単なる物質的な豊かさが喧伝される現代社会やウォール街に非常に懐疑的で、本来の豊かさや足るを知ることの意義を本書のテーマにしています。ウォール街といえば、巨額の資金が日々動き、そこから莫大な利益を得ることが重視されているイメージがあります。しかし、著者は経済的に貧しい幼少期を過ごしており、ウォール街の華々しさとはかけ離れた生い立ちを紹介しています。そこで、足るを知ることの重要性、お金を人生、成功の尺度とすることのナンセンスさを強く実感したようです。
著者がバンガードの創業者であることから、金融に関する情報も本書で綴られていますが、バンガードグループを創業するまでの経緯、ウォール街と一般的な人々との認識のギャップ、投資やファンドのあるべき姿といったものがほとんどで、投資でいかにして儲けるか、というものはありません。むしろ、長期積立投資という概念を定着させた人でもあることから、王道の投資法がどれほど強力なものであるかを論理的に示しています。短期での売買は否定的で、企業と金融市場の関係性にも言及しています。金融市場が拡大し、さらなる富を求めて過度なレバレッジをかけたり、無謀なリスクをとり続けたウォール街が、金融危機を引き起こし、実体経済に大きな悪影響を与えたことへの問題意識が伝わります。
全体を通してみると、道徳的で倫理的な内容が多く、一見すると古くさいと思えるものもあるかもしれません。しかし、当たり前の倫理観が失われることへの危機意識は、様々な人にも共感できることは確実でしょう。このお金との当たり前の向き合い方、職業に従事する人間としての心の持ちよう、精神のあり方、価値の判断の仕方、正しさといったものは極めて重要なものです。そのような本当に大事なものが、強欲で過度な資本主義社会において、忘れられている側面があることは事実でしょう。
お金と仕事と人生のより開けた視界から本質的な豊かさや幸福とは何かを考えさせてくれる良書と言えます。
この本は3部構成になっており、著者の経歴が中心となっている序章の後に、第1部のマネーをテーマにした章が3つあります。第Ⅰ章は、ファンドマネージャーやCEOの報酬、コストといった金融の産業に関する問題について、第2章では、投機、金融市場の問題について、第3章では、高いリターンを目指して複雑化する金融商品がテーマになっています。
続く第Ⅱ部はビジネスについて扱っており、第4章は、数字・計算ばかりがフォーカスされる金融の世界で、信頼に重きを置くことの意義を説明しています。第5章は、全般的な仕事の倫理観について、第6書は、投資業界における倫理について、第7章は、経営者の倫理についてがテーマになっています。著者の信念が文章から滲み出ています。
第Ⅲ部では、人生がテーマで、第8章が、物質的豊かさよりも責任を持った態度を持つ意義について書かれており、第9章では、道徳的な18世紀に回帰すべきとする主張がなされています。次の第10章では、成功ばかりを追い求めるのではなく、人格を磨くことを勧めています。最後の終章には、著者にとっての『足る』とは何かについて綴っています。
大いなる誘惑(1)
アメリカは建国以来、豊かな国であり続け、その富のために堕落することなどほとんどなかった。数世紀にわたって変わることなく、大志を抱き、勤勉に働き、倹約に努める国だった。
しかしこの30年間で、その多くが打ち砕かれた。倹約に努め、支出を収入の範囲に抑えるという常識や慣例が社会から失われていった。借金を勧め、刹那的な生き方を助長する社会のしくみが築かれた。この国の道徳を守るべき人々は、ハリウッド映画やテレビのリアリティ番組が描く退廃ばかりを追い求めている。しかし、最も手に負えないのは金銭にまつわる退廃だ。金をどのように使い、役立てるべきかについて、まともな常識が踏みにじられている。
2008年6月10日
『ニューヨーク・タイムズ』紙
デビッド・ブルックス
目次
序章
第I部 マネー Money
第1章 「コスト」より「価値」を
第2章 「投機」より「投資」を
第3章 「複雑さ」より「シンプルさ」を
第Ⅱ部 ビジネスBusiness
第4章 「計算」より「信頼」を
第5章 「ビジネス」より「職業人の行動」を
第6章 「販売精神」より「受託責任」を
第7章 「マネジャー」より「リーダー」を
第Ⅲ部 人生 Life
第8章 「モノへの執着」より「責任ある関与」を
第9章 「3世紀的価値」より「8世紀的価値」を
第10章 「成功」より「人格」を
終章 「足る」ということ
あとがき——私のキャリアについての個人的メモ
謝辞
巻末注
序章
東海岸のリゾート地、シェルター・アイランドで大富豪が開いたパーティでのこと。小説家のカート・ヴォネガットが、同じ小説家仲間のジョゼフ・ヘラーにこんな話をした。パーティの主催者であるヘッジファンドマネジャーは、ヘラーが代表作『キャッチ=22』でこれまでに稼いだ以上の金をわずか1日で稼ぐらしい、と。ヘラーはそれにこう応じた。「そうだろうとも。だが、彼が手にできないものが、私にはある。それは、「足るを知る』ということだ(1)」
足るを知る——。飾り気のないこの言葉の意味の深さに、私は打たれた。それには2つの理由があった。まず、私が人生で非常に多くのものに恵まれてきたこと。そして、ジョゼフ・ヘラーの言葉が真理をついていたことだ。たしかに、大富豪や権力者など社会の上層部にいる連中を見ていると、どこまでいっても「足る」ことなどないように思える。
私たちが生きるこの時代はすばらしい時代であり、また悲しい時代でもある。民主主義に支えられた資本主義の恩恵が、こんなにも地球の隅々にまで行きわたったことはなかった。だが同じ資本主義の行きすぎが、これほどむき出しになった時代もない。危機的状況はいまも続いている。これは、決して大袈裟に言っているのではない(2)。この危機は私たちに資本主義の行きすぎをまざまざと見せつけているのだ。投資銀行を筆頭に、銀行業界全体が、資金に過度のレバレッジをかけて過度の投機に走るのも、そしてファニーメイとフレディマックという2つの巨大な政府系住宅金融機関(「政府系」といっても民間出資の株式会社だ)のありさまも、背景にあるのは資本主義の行きすぎだ。巨大ヘッジファンドの最高経営責任者(CEO)たちが手にする数十億ドルもの年収や、この国の上場企業の経営者が受け取る「いかがわしい」としか言いようのない(ほかの表現があるだろうか)報酬については言うまでもない。経営に失敗して身を引くCEOでさえ、巨額の報酬を得ているのだ。
強欲主義が蔓延して、金融システムと企業社会の行く手を脅かしている。その弊害は金銭の問題にとどまらない。「足る」という感覚が失われると、「職業人」としての価値観が堕落する。投資のための資金を委託された「受託者」であるべき人間が、ただの「セールスマン」になり下がる。そして、「信頼」の上に築かれるべきシステムが、「計算」に基づくシステムに変わってしまう。それだけではない。「足る」という感覚がおかしくなると、人生そのものを見誤る。「成功」という名の偽物のウサギを追いかけ、長い目で見ればまるで意味のない、一時的な価値を崇めるようになる。そして、「計算」を超えたところにある不変の価値を大切にしなくなるのだ。
このことこそ、ジョゼフ・ヘラーが「足るを知る」という力強い言葉に込めた思いに違いない。富の崇拝や、職業倫理の堕落だけでなく、最終的には人格と価値観が滅びることをも見据えていたのだ。人格と価値観——。私はそこからこの本を書きはじめたいと思う。人生を通じて、私の人格と価値観がどのように形づくられたのか。そして人格と価値観によって、私の人生がどのように形づくられたのか。いずれも自分がいちばんよくわかっていることだ。読み進めていただければおわかりのとおり、私はこの人生で数えきれないほどの「足る」に恵まれてきた。
生い立ち
まずは私の先祖の話からはじめよう。
母方の祖母の先祖にあたるアームストロング家は、1700年代の初め、スコットランドから開拓者としてアメリカに渡ってきた。「スコットランド系」というだけで、私の倹約精神は十分に説明できるだろう。父方の先祖にあたるウィリアム・ブルックス・ボーグルと妻のエリザベスは、ずっと後の1870年代になってスコットランドからやってきた。まだニューヨーク湾内のエリス島に移民管理局ができる前だったが、移民の名を記した記念碑には夫妻の名前も刻まれている。
ウィリアム・ブルックス・ボーグルの息子、つまり私の祖父にあたるウィリアム・イェーツ・ボーグルは、ニュージャージー州モントクレアで小売商として成功した人物で、地元の名士だった。彼が設立した会社は、後に合併を経てアメリカン・カン・カンパニーとなった。この会社は石年間にわたり、ダウ・ジョーンズ工業株価平均を構成する3社に選ばれていた。
さらにその息子のウィリアム・イェーツ・ボーグル・ジュニアが私の父だ。第一次世界大戦がはじまると、アメリカが参戦する前にイギリス陸軍航空隊に志願し、ソッピース・キャメル戦闘機に乗った。さっそうとした、とびきりハンサムなパイロットだった。当時のイギリス皇太子(1936年にイギリス国王となったが、「愛する女性」と結婚するために退位した)に似ていたらしい。飛行機事故で負傷して帰国し、1920年に結婚した。その相手が私の母、ジョセフィーヌ・ヒプキンス・ボーグルだ。
若くて裕福な2人は、不自由なく暮らしていた。だが悲しいことに、最初に生まれた双子(ジョセフィーヌとロレイン)は生後すぐに亡くなった。1927年に1人目の息子が生まれた。私の兄、ウィリアム・Y・ボーグル3世だ。そしてほどなく、1929年5月8日に、ふたたび双子が生まれた。デビッド・コールドウェル・ボーグルと、この私、ジョン・クリフトン・ボーグルだ。
貧乏暇なし
私たち兄弟が生まれた年に、あの世界恐慌が起きた。ニュージャージー州ベローナに構えていた私たちの家も、父が受け継いだ財産も、たちまち失われてしまった。私たち家族は母方の祖父母が暮らす家に移り住み、それ以降、ニュージャージーを転々としながら苦しい時代を迎えることになる。
こうして、「足る」生活というより、むしろ「足る」以上の生活を送っていた私の家族は、あっという間に経済的苦境に立たされた。古きよき時代に何の不自由もなく育った父には祖父のような辛抱強さがなく、父は仕事を失うまいとするので精一杯だった。そんなわけで、私たちは小さいころから自分の手で稼がなくてはならなかった。「暇にしていると悪魔が寄ってくるよ」と、何度聞かされたことかわからない。
それでも、いま改めて振り返ってみて、私たち兄弟は最高の環境で育ったとつくづく思う。家計を支える責任を負うことにはなったが、自分が使う金には自分で責任をもち、自分の力で仕事を見つけ、ほかのだれかのために働く意味を知ることができたのだから。すばらしい友人たちにも恵まれ、彼らとの交友はいまも続いている。「足る」以上の生活をしていた友人たちは、私たちが働くあいだも遊んで過ごしていた。だが私たちは子どものころから、責任を与えられることや、知恵を働かせることの楽しさを知り、季節を問わずさまざまな仕事をしながら、人とかかわることの喜びを学んだ。
人生で「足る」とはどういうことか。この質問に対する私の答えは、生来の性質と若いころのさまざまな経験から形づくられたのだと思う。私は家族の強い絆に恵まれていた。誇るべき祖父母、愛情深い両親、そして喧嘩ばかりしていてもほかのだれかと闘うときには団結する、最高の兄弟がいてくれた。
ブレア・アカデミーで
7年生から8年生[訳注:日本の中学生にあたる]のころ、私と双子の兄のデビッドは、ニュージャージー州スプリングレイクの小さな学校に通っていた。その後は、家の近くのマナスカン高校に通った。
息子たちに大きな期待を寄せていた母は、最高の教育を受けさせてやれないことに胸を痛め、よい学校に通わせるために奔走してくれた。母の強い決意が実って、私たち3人はニュージャージー北西部にある名門校、ブレア・アカデミーの寄宿生となった。高い教育を受けるには絶好の場所だった。貧乏にもかかわらずこんな機会を得られたのも、息子たちの教育に熱心だった母のおかげだ。ブレア・アカデミーは私たちに奨学金を支給し、仕事も与えてくれた。私は1年生のときから給仕の仕事をはじめ、上級生になると、給仕長というやりがいのある仕事を任されるまでになった。
ブレア・アカデミーの授業はどの学校の授業よりもむずかしく、入学当初は同級生に後れをとっていた。それでも、厳しい老校長の後押しを受けてしだいに後れを取り戻し、卒業式ではクラスを代表して開式の辞を読み上げるまでになった。「精神の強さはあらゆる障害を乗り越える」。1年生のときに覚えたサミュエル・ジョンソンの言葉は、いまも私の心に深く刻まれている。